母の遺品
 ドン、ドン、ドンと、激しく表の戸が叩かれている音で目が覚めた。
ドン、ドン、ドンと、激しく表の戸が叩かれている音で目が覚めた。
急いで応対に出た父が、そのまま下駄の音を響かせて往来へ駈け出して行った。
その頃はまだ私の家には電話がなかったので、入院中の母の死を知らせる電話が近所のお家にかかってきたのであった。
やがて母は担架に乗せられて帰ってきた。
そうして、奥の間に寝かされた母の顔には白い布が掛けられていた。
その白い布の下の母の死顔を、私も当然見ている筈だと思うけれど、どうしても思い出すことができない。
祖母の手でよそ行きの服に着替えをさせられて、ただならぬ空気の充ちていく行く中で、私はただ、ガタガタと震えていた。
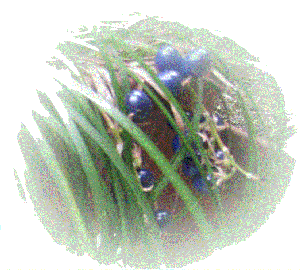 一夜が明けて、いよいよ慌ただしくなっていく家の中で、私の気持ちは妙に昂ぶっていたようだ。
一夜が明けて、いよいよ慌ただしくなっていく家の中で、私の気持ちは妙に昂ぶっていたようだ。忙しげに動く大人たちの間を通り抜けて外に出ると、隣家の前の路上で、近所のおばさんたちが4・5人かたまって立ち話をしていた。
私はそっと近づいて、「お母ちゃん帰ってきゃはったんえ、死んで帰ってきゃはったんや」と言った。
「死んで帰ってきましたんや」と、祖母が誰かに言っていたのを真似て、おばさんたちの気を引きたかったのかもしれない。
けれども、おばさんたちは一斉にエプロンの裾や着物の袖口で目頭を押さえ、
「かわいそうになぁ」と言って、泣き出した。
私はなんだか悪いことをしていて見つかった時のようなばつの悪い思いがして、急いで家に引き返した。
家に入ると、父が、台所の薄暗い通り庭に立って弔問客の前で泣いていた。
私は、とくに母の死を悲しむということもなく、むしろ、裾周りに小花のアップリケの付いた母の手編みのワンピースを着せてもらって、嬉しく、
日頃は寂しい家に大勢の人が出入りしていて、はしゃぎたい気分であった。
しかし、そうはできない、してはならない、穏やかならぬ雰囲気の中で立ち尽くしていた。
昭和17年2月初旬、私の5歳の時のことである

母はとくに身体が弱かったというわけではなかったけれど、早産しやすい体質であったらしい。
私が生まれる前にも、一度早産をしていた。しかし私が無事に生まれ育ったことで、母は自信を持ったのだろう。
本当は、もう一人生むということはとても無理だとお医者様から言われたのに、「里美が一人っ子ではかわいそうだから」と言って、
生む決心をしたのだと、後に叔父から聞かされた。しかし母は再び早産し、赤ん坊は死産、その予後が悪く、母自らも逝ってしまった。
 私の手元に黒い塗の小箱がある。
私の手元に黒い塗の小箱がある。縦12センチ、横10センチ、深さ5センチの箱で、蓋に桐の紋が入っていて、朱房の付いた紐が掛かっている。
母の嫁入り箪笥の鍵が入っていたものだと聞いたように思う。
しかし、今その小箱には一歳半くらいの私を抱いている母の写真が一枚、母が私を妊娠中に通院していた産婦人科の診察券、
お薬師様のお守り札、そして、産院の入院案内書が八つに折りたたまれて入っている。
その入院案内書を広げると、裏に女の子の名前がいくつも書いてある。
由紀子、祥代、敦子、綾子、江里子・・・・と。
夢路というのもあるが、これはぺけで消してある。
そして”里美”という名前が”サトミ”と仮名がふられていたり、苗字が冠せられていたり、楷書で、あるいは草書で、という具合に、
いくつも書かれていて、さらに一つ大きく濃く”里美”と書いて四角く囲ってある。
それは明らかに、母が私を出産した後、産院の病室のベットの上で(あるいは畳敷きの病室に敷かれた床の上であったかもしれないけれど)
私の名前を一生懸命考えていた時の様子を物語るものである。
紙片の一隅がちぎり取られているのは、そこにきちんと私の名前を書いて、見舞いに訪れた父に渡したのではないだろうか。
ようやく無事に子供を産むことができた安堵感と、母になれた女としての至福の喜びが一枚の粗末な紙質の入院案内書の裏に溢れている。
 ”サト”というのは、父の母、私にとっての祖母、つまり母にとっては姑にあたる人の名前である。
”サト”というのは、父の母、私にとっての祖母、つまり母にとっては姑にあたる人の名前である。祖母は若くして、父とその兄と姉、三人の子供を抱えて寡婦になった。苦労も多かったであろう。笑顔の少ない気難しい人であった。
何かと近所の人たちの口の端にのぼっているのを、子ども心に悲しく感じていた。
しかし、近所のおばさんたちは、いつも私に、「あんたのお母ちゃんは優しい人やったえ」と言ってくれた。
それは勿論、早逝した人間に対する弔意であり、幼くして母を亡くした子供への憐憫ではあったろう。
けれども、初めてのわが子に姑の名前にあやかった名前を付けた母は、祖母にとってはかけがえのない優しい”嫁”であったのだろうと思われる。
母が亡くなった時「死んで帰ってl来ましたんや」と言った祖母の落胆の大きさが改めて思われる。
母が逝って三年後、祖母も他界した。

高校を卒業したばかりの頃だったと思う。ある人から私の名前の字画がよくないので、字を変えてはどうかと言われたことがあった。
幼時からの幸いの薄さを言い当てられたようで、少し気持ちが揺らいだ。
けれど、たとえ落書きのようなものであっても、母の手によって書き残された名前の字以外に私にふさわしい字はないように思えて変えることはできなかった。
ただ、私がまだ子供の頃父が、「お前の名前は、子供の間はええけど、おばあさんになったら似合わんようになる。そしたら”美”を取ったらええで」と言ったことがあった。
”美”を取って”里”なのか、”さと”なのか、”サト”なのか、そこまでは聞かなかった。
いずれにしても、還暦も過ぎたことだ。そろそろ”美”を取らなければと思いながら、なんとなくまだよう取れずにいる。
(1997年5月・記)
追 記
もうすぐ母の忌日2月8日が来る。
あの日から70年が経った。
そして、私もとうとう後期高齢者の仲間入りをした。それでもいまだ”美”は取れないでいる。
(2012年1月8日・記) 戻る