瀬戸内晴美の作品を拾い読んで

瀬戸内晴美の作品を拾い読んで

私が瀬戸内晴美の小説を初めて読んだのは毎日新聞の朝刊に連載された「妻と女の間」(昭和43年)であり、次に読んだのが、やはり毎日新聞朝刊に連載された「まどう」(昭和51年)であった。いずれもごく平凡な生活をしている私には考えられないような男女の関係が生々しく描かれていて、読むことすら気恥ずかしさを憶えるような場面が多くて、とても文学作品として読み取る余裕はなかった。戦後いかに愛欲描写の大胆な映画や読み物が氾濫してきたとはいえ、朝の目覚めに読む新聞小説にしてはいかにも生々しすぎて、以来、瀬戸内晴美の作品に関心はなく、読んだことがなかった。
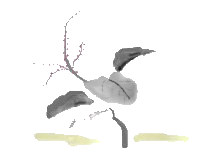
ところが一昨年、梅雨空の下、河野先生ご案内の文学散歩で、八瀬から濃霧の比叡山へ上り、先生から瀬戸内晴美の「比叡」についてのお話を聞いて、やはり瀬戸内作品も読んでおかなければと思い「比叡」と、他にも「女徳」「嵯峨野日記」「私小説」を買い込んだ。しかし最初に「女徳」を読んだことが間違いで、また躓いてしまった。
情欲のままに生き、出家をして世を捨てるという女性の生き方は私には理解できず、愛欲描写の多さに、とても瀬戸内晴美の世界にはついていけないと諦め、せっかく買った他の本は本箱の奥に押しやっていた。
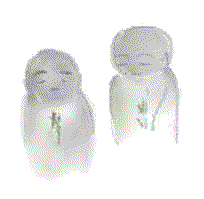
それからしばらくして、「京都現代文学を楽しむ会」の読書会のテーマに「比叡」が取り上げられ、再び気を取り直して読んだ「比叡」は、夫の死と向き合い夫の命に寄り添って過ごす日々の中で読んだせいもあって、それまでに読んだ作品と違って、仏教的なことは一切分らないながら、徳度の場面や比叡山での修行の場面の荘厳な様に心が引き込まれたし、続いて読んだ「嵯峨野日記」では、嵯峨野の庵での日々の出来事や心情が流麗な筆致で描かれていてその表現の妙に感心した。さらに「私小説」に描かれたさまざまな人の病と死、とりわけお姉さんの病状と死に様は切実なものが胸に迫って辛く、しかしその辛さを我慢しつつ読まずにはいられなかった。
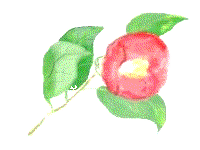
「比叡」を読んでいるときは私も夫を送ったら出家でもしてしまいたいような気持ちであったのが、幸か不幸か、私には世を捨てるだけの勇気も信仰心もなく、多くの仲間、友人、兄弟、子供たちに支えられ、先に逝った夫に申し訳ないと思いつつ俗世で生を享受している、。
「やっぱり女は強いなぁ」と揶揄と安心のない混ざった顔で弟が云う。そういえば瀬戸内晴美さんも「嵯峨野日記」の中に「妻に先立たれた夫はひたすらみじめで痛ましいが、夫に先立たれた妻は、淋しいけれどゆたかさとすがすがしさが感じられるのはどうしてだろうか」と書いておられる。私もできるだけゆたかですがすがしい生き方を心がけていきたいと思うのである。
1991年10月30日・記
戻る